個人市民税・県民税(納税義務者と課税内容)
日常生活に欠かせない、道路・橋梁・公園の設備から、教育、福祉、消防・救急、下水やごみ処理など、さまざまな行政サービスのために必要な経費を、できるだけ多くの住民の方に税金として広く負担いただくものとなっています。
市民税・県民税は、税金を負担する能力のある方全てが均等の税額を納める均等割と、その方の所得金額に応じて納める所得割で構成され、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で前年中の所得に基づき課税されることになっています。
均等割と所得割
均等割
一定の所得以上のとき、均等の額を納めていただくものです。
- 市民税=年額3,000円
- 県民税=年額2,000円
所得割
その人の所得金額などに応じて納めていただくものです。
- 税率=10パーセント(内訳=市民税6パーセント、県民税4パーセント)
森林環境税
令和6年度から、国内に住所を有する個人に、市民税・県民税の均等割と併せて年間1,000円の森林環境税が賦課徴収されています。
詳細は下記リンクを参照ください。
納税義務者
毎年、賦課期日(1月1日)現在、相馬市にお住まいの方や、市内にお住まいではなくても、相馬市内に事務所、事業所または家屋敷がある方には、市民税・県民税が課税されます。
| 納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
|---|---|---|
| 市内に住所のある人 | 課税 | 課税 |
| 市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷がある人(注意1) | 課税 | ― |
(注意1)事務所、事業所や家屋敷がある方に課税される均等割
- 事務所、事業所や家屋敷などがあることによって受ける基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備など)に対して、一定の負担をしていただく必要性から、市民税・県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項および第294条第1項)
- 家屋敷とは、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状況にある建物をいいます。
均等割・所得割ともに課税されない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得が135万円以下(給与所得のみの場合、年収204万4千円未満)の方
- 扶養親族等がいない方で前年中の合計所得金額が38万円以下の方
- 扶養親族等がいる方のうち、前年中の合計所得金額が、28万円に控除対象配偶者、扶養親族、本人を足した数を掛けて、10万円を加算した金額に16万8千円を足した金額以下の方
(注意)民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
所得割が課税されない方
- 扶養親族等いない方で、前年の総所得金額等が45万円以下の方
- 扶養親族等のいる方のうち、前年の総所得金額等が、35万円に控除対象配偶者、扶養親族、本人を足した数を掛けて、10万円を加算した金額に32万円を足した金額以下の方
納付方法
給与特別徴収
会社員などの給与所得者の市民税・県民税を事業主(給与支払者)が毎月の給与から天引きし、その年の6月から翌年5月まで各個人に代わって事業主が納付する方法です。
詳細は下記のページをご覧ください。
普通徴収
普通徴収とは、市から送付された納付書により各個人がコンビニ、金融機関や市役所で直接納付する方法です。納付回数は、通常4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分かれています。
(注意)口座振替制度もありますので、利用を希望する方は各金融機関で手続きをお願いします。
年金特別徴収
公的年金にかかる市民税・県民税を年金から天引きする制度です。
以下の要件の全てに該当する方が年金から特別徴収されることになります。
- その年度の初日(4月1日)現在において65歳以上の方で老齢基礎年金等を受給している方
- 公的年金にかかる所得に対して、市民税・県民税が課税されている方
- 介護保険料を公的年金から天引きされている方
- 公的年金を年額18万円以上受給されている方
詳細は下記のページをご覧ください。
所得金額の種類および算出方法
所得の種類
所得金額の種類は10種類あり、その金額は一般的に収入金額から必要経費を差し引くことで算出されます。
- 利子所得:公債、社債、預貯金などの利子
- 配当所得:株式や出資の配当など
- 不動産所得:地代、家賃、権利金など
- 事業所得:事業をしている場合に生じる所得
- 給与所得:俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得
- 退職所得:退職金、一時恩給など
- 山林所得:山林を売った場合に生じる所得
- 譲渡所得:土地などの財産を売った場合に生じる所得
- 一時所得:懸賞金、生命保険金など
- 雑所得:公的年金、原稿料など他の所得に当てはまらない所得
非課税所得の種類
所得の中には市民税・県民税がかからない「非課税所得」があります。非課税所得は、所得税法および租税特別措置法のほか、その他の法律に規定されています。主な非課税所得には、以下のようなものがあります。
- 障害年金
- 遺族が受ける恩給や年金
- 雇用保険の失業給付金
- 生活保護のための給付
- 通勤手当
- 相続、贈与によって得た資産(相続税や贈与税の対象になります。)
- 児童手当、児童扶養手当
- 健康保険の保険給付金、育児休業手当金など
各所得金額の算出方法
各所得金額の算出方法は、下記のPDFを参照ください。
所得控除
所得控除とは、納税者に配偶者や扶養親族等があったり、医療費の支出があったりしたときなどの個人的な事情を考慮して、負担の不均衡を調整し、能力に応じた税負担を求めるために総所得金額から一定の金額を控除するものです。
詳細は下記のPDFを確認ください。
税額控除
税額控除とは、所得控除が税率をかける前の所得金額から一定の金額を控除するものであるのに対して、税率をかけて算出した税額から一定の金額を控除するものです。
詳細は下記のPDFを確認ください。
税額計算方法
税額の計算方法例は、下記のPDFを参照ください。
定額減税
賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度及び令和7年度市民税・県民税において、定額減税が実施されています。
詳細は下記リンクを参照ください。
個人市民税・県民税に関するよくある質問と回答
質問1:昨年(令和6年)12月に仕事を辞め、その後無職無収入にもかかわらず納税通知書が届きました。どうしてですか?また、働いていませんがこの税金は支払わないといけませんか?
市民税・県民税は、前年中の収入を基に計算されます。そのため、令和7年度の納税通知書に記載された税額は、あなたの令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の給与収入を基に計算されます。現在の収入にかかわらず支払わなければなりません。
質問2:昨年と収入がほぼ変わらないのに税額が増えたのはなぜですか?
市民税・県民税は、収入(所得)と所得から差し引く控除額に基づいて算出されます。そのため、収入金額が変わらなくても、昨年より所得控除額が減ると税額は増えることになります。所得控除額は、税額決定通知書を確認ください。
質問3:令和7年4月1日に相馬市からA市に引っ越しました。令和7年度の市県民税は、どちらに納めることになりますか?
市民税・県民税は、1月1日にお住まいの市町村で課税されます。あなたの場合、令和7年1月1日時点では、相馬市に住民登録があるため、令和7年度の市県民税は相馬市に納めることになります。(令和7年度は、A市では課税されません)
質問4:令和7年2月に夫が死亡しましたが、夫の名前で令和7年度の納税通知書が届きました。納める必要はありますか?
市民税・県民税は、1月1日にご存命の方へ課税されます。そのため、2月に亡くなられた場合でも令和7年度の市民税・県民税が課税され、1年分の税額を納めていただくことになります。
また、納税義務者が亡くなられた場合は相続人が納税の義務を承継することになります。
質問5:夫の扶養に入っているのに納税通知書が届きました。扶養に入っていれば、市民税・県民税は課税されないのではないですか?
給与収入が103万円以下であれば扶養に入ることができます。しかし、給与収入が93万円を超えると年間6千円の市民税・県民税(均等割及び森林環境税(国税))が課税されます。
(注意)年齢や障害の有無など、本人の状況により計算方法などが異なる場合があります。
質問6:子どもがアルバイトをしていますが、いくらの収入ならば市民税・県民税がかかるのでしょうか。
一般的に給与収入で年収93万円(所得38万円)を超えると市民税・県民税が課税されますが、お子さんが未成年者である場合、年収204万4千円未満(所得135万円以下)であれば市民税・県民税は課税されません。
しかし、年収103万円(所得48万円)を超えた場合は、所得税が課税され、さらに扶養控除の対象から外れます。
(注意)未成年者とは、市民税・県民税がかかる年の1月1日時点において、18歳未満で、結婚していないまたは婚姻歴のない人になります。
質問7:税務署で所得税の申告をしましたが、市民税・県民税の申告も必要ですか?
確定申告をされた場合、後日、確定申告書の写しが市役所へ送られてきます。それが市民税・県民税の申告書になりますので、市民税・県民税で別途申告していただく必要はありません。
ただし、市役所に確定申告書の写しが到着するまで2、3カ月時間を要しますので、お急ぎの方は市役所でも市民税・県民税の申告もしくは確定申告書の写しの提出をお願いします。
質問8:税務署から、所得税がかからないため確定申告の必要はないと言われました。市民税・県民税の申告も必要ありませんか?
所得税と市民税・県民税では、税金の計算方法が異なります。所得税がかからない場合でも、市民税・県民税がかかり、申告が必要な場合がありますので、詳細は市役所1階税務課に問い合わせください。
質問9:前年中の収入がなかったのですが、申告する必要はありますか?
前年中収入がなかった場合、所得税の確定申告は基本的に必要ありません。しかし、市民税・県民税の申告をしていないと、国民健康保険税の軽減措置を受けることができない、所得・課税証明書などの各種証明書の交付を受けることができないなど、さまざまな支障をきたすことがありますので、収入がなかった場合でも、市民税・県民税の申告をお願いしています。
また、課税の対象とならない遺族年金や障害年金などの収入のみの場合でも、同様に申告をお願いしています。
質問10:給与所得者ですが、原稿料の所得が15万円程度あります。所得税は副業の所得 が20万円以下であれば申告不要ですが、市民税・県民税の申告は必要ですか?
所得税の場合は、所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされています。しかし、市民税・県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、ほかの所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず、市町村に申告しなければなりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
- あなたの評価でページをより良くします!
-
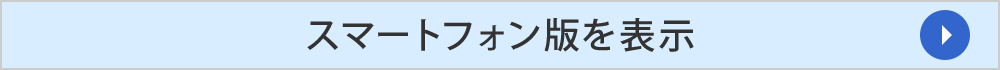


更新日:2025年10月20日