KM-43 主な漁法
漁業(ぎょぎょう)にはむずかしいことばがたくさん出てきます。
まずは、漁法(ぎょほう)を学ぶ前に、まめ知識(ちしき)で予習しましょう。
まめ知識
- 船が港を出ることを出港(しゅっこう)、かえってくることを帰港(きこう)といいます
- 船のかぞえ方は一般的(いっぱんてき)に大型の船は1隻(いっせき)、2隻(にせき)、中型から小型の船は、1艘(いっそう)、2艘(にそう)です。
- 船などの機械(きかい)をうごかして作業することを操業(そうぎょう)といいます。
試験操業のはなし
平成29年4月1日から試験操業(しけんそうぎょう)をおこなっています。
現在、福島県がおこなっている放射性物質(ほうしゃせいぶっしつ)モニタリングで、魚介類(ぎょかいるい)の安全性が確認(かくにん)されています。(令和元年5月現在)
沖合漁業(おきあいぎょぎょう)
重さが15トン以上の漁船をつかっておこなう漁業です。
出港してから帰港するまで1~3日間かけておこないます。
沖合底曳網(おきあいそこびきあみ)
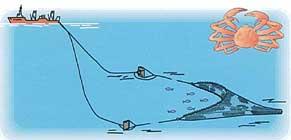
袋状の網(ふくろじょうのあみ)を海の中でひき、底層(ていそう)に分布(ぶんぷ)する魚などを漁獲(ぎょかく)します。
15トン~50トン未満の船が、カレイ類、ヒラメ、タコ、カニなどを対象(たいしょう)に操業(そうぎょう)します。
沿岸漁業(えんがんぎょぎょう)
重さが7トン未満の漁船をつかっておこなう漁業です。
沿岸に近いところでおこなわれます。
沿岸漁業には小型底びき網、刺し網(さしあみ)、船引き網、延縄(はえなわ)、釣り(つり)、カゴ、筒(どう)、貝桁網(かいけたあみ)、潜水(せんすい)などたくさんの漁法があります。
固定式刺網(こていしきさしあみ)
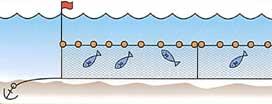
魚の移動路(いどうろ)にナイロン製の網をしかけ、移動中の魚を網目(あみめ)にさしたり、からめたりして漁獲します。
朝1時ころ出港して漁場にいき、セットしてある網を2時間くらいかけて引きあげます。
沖合10メートルから20メートルのポイントで漁をおこないます。相馬港から船で30分から40分の距離(きょり)です。
7トン未満の漁船が、カレイ類、ヒラメ、タラ、メバルなどを対象に操業します。
県北部の主要漁業(しゅようぎょぎょう)です。
船引き網(ふなびきあみ)
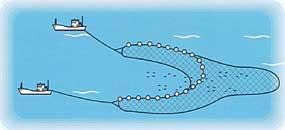
空が明るくなる朝4時ころ出港して、昼間まで操業をつづけます。
袋状の網を海中でひき、表層、中層に分布する魚などを漁獲します。
1隻でおこなう場合と、2隻でおこなう場合があります。
7トン未満の漁船がオキアミ、イワシシラス、コウナゴ、シラウオ、サヨリを対象に操業します。
延縄(はえなわ)
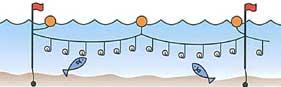
朝、明るくなる前から漁にむかいます。
一定の間かくをおいて針(はり)がついている延縄漁具(はえなわぎょぐ)を海の中に設置(せっち)し、えさにさそわれて針にかかった魚を漁獲します。
針には貝やサンマの切り身などをつけます。
7トン未満の漁船が水深(すいしん)50メートルより浅いところでアイナメ、スズキなどを対象に操業します。
貝桁網漁(ホッキ貝漁)

マンガという漁具をつかってとるホッキガイの漁法です。これは、ホッキガイが砂場にいるためです。
船の両端(りょうはし)にマンガをつけて、ワイヤーをまきあげて砂の中からホッキガイをとります。
6月から翌年の1月末までおこなわれます。
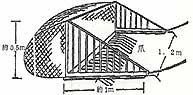
マンガ拡大図
タコかご漁
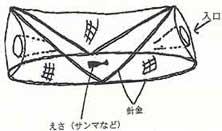
かごを海にしこんでタコをつかまえる漁法です。
水深40~50メートルの浅い沿岸にタコかごをしかけます。ひとつのしかけで十数個(じゅうすうこ)のタコかごをつかいます。
タコかごの中にはサンマの切り身などのえさをしかけ、タコが一度はいったら出られないつくりになっています。
ノリ養殖について
ノリの養殖は9月から翌年の4月ころまでおこなわれます。
9月ころ、松川浦に竹と網でのり棚(のりだな)を設置(せっち)して、その棚にノリの種(たね)をうえこみます。
12月ころ、成長したノリのかり入れがはじまります。
ノリがとれる時期は12月から翌年の4月までです。とてもさむく、海が冷たいためとても大変な作業です。
アサリについて
松川浦では、アサリ漁もおこなわれています。
(注意)東日本大震災がおきる前までは潮干狩り場があり、3月中旬から8月にかけて毎年おおくの観光客(かんこうきゃく)がおとずれていました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農林水産課 水産振興係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2152
- あなたの評価でページをより良くします!
-
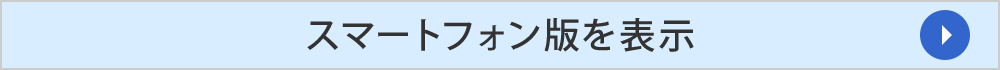


更新日:2020年01月14日