No.302(2016年5月2日号)地方病院と女医さんのピンチ
平成29年度から実施しようとしている専門医の仕組みについて、日本医師会や病院団体から異論が吹き上がっている。平成26年5月に設立された一般社団法人日本専門医機構が、専門医の認定と養成プログラムの評価・認定を統一的に行うこととなっているが、医療の現場、特に地域医療を担う地方の中小病院にとっては厳しい現実が予想される。
ここで云う養成プログラムが問題なのである。指導体制などの厳しい基準や期間などの要件を満たせるのは、ほぼ大学病院に限られる。つまり地方病院の指導医の下での臨床経験では、専門医取得基準を満たせないことになるのだ。地方への配慮として地域内での他病院での研修なども認めると云うが、常勤でもない一定期間だけの若い医師のお手伝いを、戦力に数える院長はいないだろう。
医療の質の向上を目的とした議論が喚起されるのは結構なことだが、現場の医療状況を無視して、理想論だけで実質的な規制が走り出しては困るのだ。厚生労働省は「制度」ではなくてあくまで「仕組み」と表現しているが、近い将来、標榜科に対する規制などが実施されれば、専門医を多く抱える都市部の大病院でないと医療ニーズに応えられなくなる。だからこの問題は、「仕組み」などとお茶を濁さず堂々と国会で議論すべきだ。
もうひとつ。
女医さんの出産の問題がある。おそらく多くの初期研修修了者が専門医を目差さざるを得ないだろうから、ストレートで初期研修を終えた女医さんでも30歳すぎまでは出産が厳しくなる。新しい専門医取得のためには、長期の休暇取得は難しいのだ。医療の質の向上だけを唱えて、地方の医療供給体制の足を引っ張り、女性の子育て・出産の足かせになるような制度は考え直すべきである。
実は、私が震災復興に全力を傾ける相馬地方でも深刻な実例がある。
今年の4月に仙台市の研修病院から南相馬市立病院に麻酔科の後期研修医として赴任した28歳の既婚の女医さんは、志が高く、被災地であるこの地で出産・子育てをしながら頑張りたいという。しかし、この「制度」が始まれば彼女の健気な気持ちは到底かなわない。
女性の社会進出においては民主的であるべきだ。女医さんもしかりである。
せっかく医学部を卒業して国家試験にも合格した優秀な女性であるが故に、子どもを産む自由を制限されるとしたら、憲法の精神にも反するのではないだろうか?
- この記事に関するお問い合わせ先
-
秘書課 秘書係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2115
- あなたの評価でページをより良くします!
-
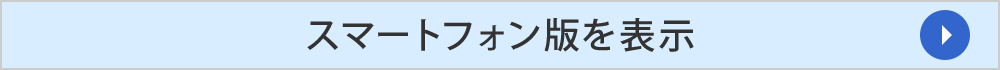


更新日:2019年07月02日