メールマガジンNo.300(2016年3月4日号)「何をば語りたもうや」
この美しい女性と、私は今日初めて出会いました。
私に何か言いたげな面持ちのセピア色の写真。
日本女性の凛とした美しさと、どことない愁いを感じます。
彼女に関して多少の事はわかっていましたが、写真を見たのは初めてでした。
この写真が撮影されたのはおそらく1927年。
88年前の事です。
彼女は現在の福島市飯野町の出身。
東京の女子美術学校を卒業して、同じく福島県から京都大学に遊学していた男と知り合い、そして結ばれ、ふたりは朝鮮の釜山に渡りました。
写真はその時代に釜山の写真館で撮られたものと思われます。
ふたりの間にできた男の子を一人残して、その後、悲しくも彼女は23才で亡くなりました。
私がこの美しい女性と、今日まで出会うことが無かったのには訳があります。
この写真は、東日本大震災の津波で流されていた持ち主不明のアルバムの中にありました。
88年前、幼い男の子を残して彼女が亡くなったあと、男は一念発起して、東北大の大学院で経済学に打ち込みます。
仙台の女性とその後に再婚。
遺された男の子に後妻は惜しみ無い愛情を注ぎました。
そして一族は、物心つかない男の子には、本当の母親でないことをひたすら隠して育てました。
後年、青年期になった遺児が産みの母の事を知り、母のふるさとを訪ねたとき、遺児の祖父母は一目でわかったそうです。
後妻は遺児の成長を写真に修め、節目ごとに報告していたからです。
そして遺児は、実の母を知ったことを決して顔に出しませんでした。
実の母が亡くなった後、一族が迎えた後妻は、ひたむきな、いつも謙虚で控え目なひとでした。
その人格に応えるが故に、また遺児への秘密を守ろうとしたが故に、革表紙のアルバムに納められた実の母の写真は、決して遺児の眼に触れぬよう、土蔵の奥にひっそりとしまいこまれていたのです。
それが、大震災の津波に打たれ壊された土蔵から流れ出て、ボランティアに拾われ、瓦礫の泥を洗われ、持ち主不明写真の棚の上に置かれていました。
浜にしては瀟洒(しょうしゃ)な、革表紙の古いアルバムに何気なく目を留めた遺児の妻が、夫の母親のアルバムと気付き、訳を話して持ち帰りました。
そして優しかった姑への義理により、ひとに見せることなく大切に保管していたのです。
今日、入院先の病院から帰宅した高齢の遺児の妻は、きっと彼女が私の手を招いたに違いない、大事なものだから預かって欲しいと息子に託しました。
それでこの写真(注意1)が、いま私の手元にあります。
そう。
その遺児とは、私の父親。
この女性は、私の祖母なのです。
成人となった後、画学生だった母親が遺した自画像(注意2)を入手した私の父は、何よりも大切な宝にしてきました。
感謝尽くせぬ育ての親を看取った後、私が見せてもらったその自画像は、自らの内面を洞察する感性豊かな絵だと思います。
ところがそこに描かれた女性は美しさとは程遠い人でした。
しかし父には人生を勇気付けてくれる大切なお守りだったのです。
父の心を励まし続けた祖母は、母の手を招いて、孫の私に何を語らむがために来たのでしょう。

(注意1)の写真

(注意2)の自画像
- この記事に関するお問い合わせ先
-
秘書課 秘書係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2115
- あなたの評価でページをより良くします!
-
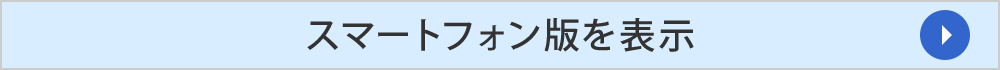


更新日:2019年08月08日