メールマガジンNo.298(2016年2月16日号)中間報告ダイジェスト
地震に続いて入って来た津波のニュースに騒然となりながら、ホワイトボードに書き込まれる情報をカメラで逐次記録するよう総務課の伊東君に指示した。
経験したこともない想像を絶する災害だから、今起きていることを冷静に分析しながら進まなくてはならない、事象や数値を消しながらでは基礎データにならない、と咄嗟に考えた。
その夜の会議から対策会議のテーマと対策の方法論を一枚のシートに表現し、さらに発言録を建設部長の小山君がコンピューターに入力し始めた。
震災から数日後には、この未曾有の体験を後世に伝えることも今の相馬市としての義務ではないか?という意識が芽生えるようになっていった。
あれからもうすぐ5年。
感慨にふけるには、まだまだ途上の仕事が多すぎる。
復興のためのハード事業についてこそ、何とか先々の見通しは立っているものの、何時まで続くか知れない風評被害をはじめ、空間線量が弱まったとは言えまだまだ気を抜くことが許されない放射能からの健康対策、子どもたちへのPTSD対策、そして何より基本である津波被災者の生活再建。
集中復興期間が5年とされたため、2016年3月11日を目前にして多くのマスコミからアンケートが来た。
中には、「あなたは現在の復興状況を何パーセントと考えますか?」という能天気な質問もあった。
多くの市町村長が回答を拒否したらしいが、特に福島県の場合、地震・津波・原発事故という3つの災害が入り組み過ぎて、ゴールの設定が出来ない。
ハード事業だけなら「予想必要事業量に対し、何パーセント発注済」のような数値化が出来るだろうが、人々の社会的、経済的、精神的な復興と生活再建となると、そうはいかない。
だいいち、次々と起きてくる社会的問題や行政課題に対して、今日の段階で固定化することなど出来るはずがない。
しかし、この4月からは「復興創生期間」がスタートするし、相馬市としても平成28年度にはこれからの10年を見渡した相馬市総合計画「2017相馬市マスタープラン」を市民と総力で作る予定である。
そこには、苦しかったけれども市民みんなで頑張ったこの5年間の歩みを踏まえて、次世代に希望と未来をつないでいく英知を結集しなくてはならない。
そんな思いもあってこの5年間の相馬市の震災対策と復興の状況を100ページにまとめたダイジェスト版を編集した。
海外からの支援者にもご報告したいので、英訳版も作成する。
私はこの手の事業を外注に出したのでは、本当に必要なことを決めることも伝えることも出来ないし、職員のプレゼン能力も向上しないと考えて、全て自前で作るように指示してきた。
今までの中間報告も職員たちの作品である。
今回の編集は情報政策課の奥山君が頑張った。
説明の分かり易さや見やすさなどの点で良く出来ていると思う。
内容は大きく4部から成っている。
最初は急性期ともいえる震災2週間の対策会議の記録。
次にその後の復旧・復興へのトピックス。次に放射能対策の数々と実際のデータ。
最後にハード事業のうちの完成分の一覧である。
お世話になった事例などを多く載せたかったが、紙面の関係上割愛させてもらった画像も多かった。
改めて振り返ってみて、やはり急性期の2週間は全力疾走だったように思う。
マスコミが来て、「不眠不休の対策で大変でしょう?」とよく言われたが、私も職員も市民も、大変だなどと思う余裕は無かったし、弱音を口にするものもいなかった。
あの時はじっくり考える余裕など無く、次々に対策の指示を出さなければならなかった。
その数々の決断への評価は、後世の検証に委ねるしかないと思う。
しかし、この5年間の最も大きな感慨を吐露するとしたら、「相馬市民のまとまりと粘り強さ」に尽きる。
700年この地で培ってきた相馬の武士(もののふ)の精神や、近世の報徳仕法の「至誠」による大きな力があったように思える。
相馬の歴史と風土である。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
秘書課 秘書係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2115
- あなたの評価でページをより良くします!
-
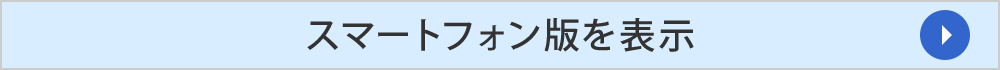


更新日:2019年08月08日