メールマガジンNo.296(2016年1月4日号)市民との協働
10年ほど前。
「市民との協働による地域づくり」というキャッチコピーが流行った。
ところが具体的にどうするのかというと、なかなか実効ある方法が出てこない。
タウンミーティングを開いて市民の意見を聞く形で、地域社会の中に入って協議をすることも一つの方法だから、友人の市長たちの中には積極的にその活動を続けている人たちもいるが、たいていは都市部の市長たちである。
実は私も、就任間もないころに市内の9方部でタウンミーティングを持ったことがある。
ところが、集まる人が少なかった。
9会場で合計520人しか集まらなかったのである。
市長が地域の要望に答えるのだから、予算や段取り、今までの経過や条例上の問題などを踏まえてお答えしなくてはならないので、全員の部長さんたちを連れて臨んだのだが、出てくる話はほとんどが自宅前の道路の舗装や側溝に蓋をかけろなどの話ばかりだった。
ある部長から、来年もこんなことをするならあんたがなんと言おうと俺は降りさせてもらうからと、公然と市長の指示に反逆する発言が出て、私自身、民意の汲み取り方の難しさを実感させられた苦い経験がある。
もしも私が地域の中に直接飛び込んで要望の解決策を提示するようなことをすれば、市役所の組織が持たなくなるからである。
「市民との協働」という理念を実現するのに二つの方法がある。
一つは、市民の要望や悩みを直接聞いて政策に反映させること。
もう一つは、市民の希望や市の政策を実現するにあたり、政策形成や実行段階で参加協力してもらうことである。
昨年、地方創生総合戦略を練り上げるにあたって、各地域で説明会を行った上で、市民アンケートによる意見を市役所が補足する形で原型を作り、団体や市民の代表からなる検討会議の議論を整理する方法で策定したことは、前回のメルマガで紹介したとおりである。
以前には市民会館の外観デザインや、新しく建設する市役所の基本デザインの意向調査を全戸アンケート方式で行っている。
また昨年10月中旬から始めた、「市長への手紙」の反響も大きく、昨年だけで140通のお手紙を頂いた。
電話で話せば本音も聞けて、中には、「あんたが逃げろと言わなかったお蔭で、原発の補償を貰えない。みんな恨んでいるぞ!」といったお叱りもあって、市民の本音を垣間見ることが出来る貴重な事業と思っている。
一番多いのはやはり地域整備に関することで、道路改良から始まり、こんな施設を造ってもらいたいというのもある。
私はこれを各担当課に降ろして実情を検証し、改善すべきもの、新たに政策として打ち出す検討に入るもの、それから到底不可能なご要望(例えば墓所の道が悪いから改良してくれ。しかしその道はお寺の私道で私には手が出せない)に分けて対応策を協議し、それぞれの投簡者に電話でお答えした上で、文書で正式なお返事を出すことにしている。
中には今後相馬市として取り組まなければならない未来に向かっての提言(例えば、企業誘致に伴い九州から相馬に移り住んでここで骨を埋める。しかし墓地が無いから、自分と同じ立場の人たちの為にも市営の共同墓地を作ってほしい)もあり、電話でお話しすることが楽しい息抜きになっている。
二つ目の実行段階での市民の協力、市民との協働という意味では、相馬市は先端を行っていると自負している。
例えば光陽サッカー場。
天然芝3面、人工芝2面にクラブハウスを備える日本サッカー協会公認の、相馬市ぐらいの地方都市には稀な一流のサッカー施設だが、もともとは石炭灰の埋め立て処分場に、粉塵舞い上がり防止の為に植えた野芝を刈って、草サッカー試合をしたいという相馬のサッカー愛好者たちの要望から始まった事業である。
震災の2年前、要望に来た市会議員の植村さん(現相馬市議会議長)に、「相馬市の施設になるのだから管理運営をしなくてはならない。
それも5面も作るとなると、芝刈りから水撒きから大変な仕事になりますが、皆さんがNPOとして管理委託を引き受けてくれるならやりましょう」と言って始まった事業である。
震災の津波の被害も出たが、被災した子供たちがNPOの管理指導の下に元気にサッカーをする姿が、日本サッカー協会の心に響いた。
日本サッカー協会はFIFAから復興支援に寄せられた基金で、5面のうち4面を整備してくれたのである。
以来、全国の有名選手や指導者を派遣いただいていることや、広域的に大会が催されることは、原発の風評被害で交流人口の減少に苦しむ相馬市にとってまことに貴重な社会活動だが、管理運営はすべてNPOの手になる。
同様に、一昨年去年と福島県市町村対抗ソフトボール大会を開催した光陽ソフトボール場、光陽パークゴルフ場、松川浦環境公園、震災後に民俗資料を保存公開するために復興効果促進事業で建設した相馬郷土蔵、などもそれぞれのNPOが指定管理者となって管理運営をしてくれている。
また、ソフト事業となるが、集落の独居高齢者のお宅をヤングオールドが声掛けして廻る「ライフネット相馬」や、被災した小中学校のみならず、市内の私立学校に臨床心理士を派遣してPTSD対策や心のケアを行っている「相馬市フォロアーチーム」の活動もNPOに対する委託の形式をとっている。
もしも、これらの事業を市の直営で行ったとしたら、費用が膨大になるばかりか、対象者の声を直接事業に反映させるという点で、難しかったろうと思う。
NPOに委託という手段は、市からの予算措置に対して明確な決算書を以って事業の透明化を図るという点で合理的である。
また事業の継続性や不慮の事故への対応や責任の所在という視点からも有効である。
被災した尾浜地区に、住民の方々をはじめ関連する団体のご意見も入れて、市民の手で整備計画を策定中の多目的広場などは、完成後は地域の方々にNPOを結成してもらい、管理運営も地域の方々にお願いしたいと考えている。
予算の問題などもあるが、計画立案から最終的な運営まで市民、特に被災者の方々に主役になってもらえば、協働による復興の形が実現する。
海岸沿いに出来る防災緑地の完成に合わせて共用できるよう整備を目差したい。
しかし、市民の活動の中にはもっと緩やかな繋がりで社会貢献をしている団体も数多くある。
集落での環境維持や、文化活動などにはNPOとしての事務がなじまない事業も多い。
今年はそれらも含めて、出来るだけ市役所が把握した上で、「市民との協働」というテーマで支援させて頂くことを考えたいと思っている。
復興から地方創生に向かうために、市民が主役になって活躍してもらえる相馬市を目差していきたい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
秘書課 秘書係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2115
- あなたの評価でページをより良くします!
-
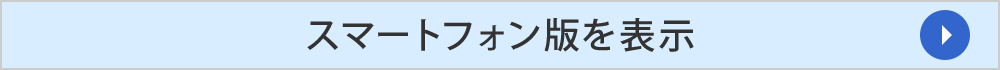


更新日:2019年08月08日