メールマガジンNo.261(2011年11月21日号)ブータン国王陛下
11月18日。ジグミ・ケサル・ナムギャル・ワンチュク第5代ブータン国王陛下ご夫妻が、ご結婚後初の日本訪問の公式行事の合間をぬって、被災地激励のために相馬市をご訪問されました。前日からメディアでも大きく取り上げてられていたため、相馬市民のみならず各地から、ひと目でいいからお会いしたいとの電話を数多くいただきました。相馬市滞在のご予定の90分のうち前半の40分が桜丘小学校での子どもたちとの交流、後半の40分が私の担当で被災地を視察されたいとのご希望でした。お若くておきれいな王妃を伴ってのご旅行は、日本にも、相馬市にも大きな希望を与えましたが、特に、桜丘小学校の生徒たちには貴重な経験になったと、有難く存じております。こころを込めて練習した小学生たちの歌声を聴いていただいた上に、国王が信条とされている「あなたの心の中にいる竜を鍛え育てよ」という力強い教えを受けた子どもたちの今後が楽しみです。
ブータン国の歴史は決して平穏なものではありませんでした。19世紀までは国内の宗教対立を伴う部族間の抗争が続き、また隣の大国チベットからの圧力にさらされ、小国ゆえの苦労が絶えなかったようです。1907年、それまで地方の有力豪族だったワンチュク家が支配権を確立し、世襲王朝制をとってからの一世紀は統一王国としての統治がなされてきましたが、人口70万人の小国が激変の20世紀のアジアを生き抜くには、先代までの国王のご苦労は大変ものだったろうと推察されます。現に、かつてブータン国に幾度と攻撃を仕掛けてきたチベットは、国家としては既に存在していません。
5年前、国王に即位されたジグミ・ケサル・ナムギャル・ワンチュク陛下はまだ31歳。しかしこの間、立憲君主制への移行という大仕事をすでに成し遂げられています。いたずらに西洋化を進めず、民族衣装を纏いながら、伝統と信仰に生きようとする国家理念は、現代文明に振りまわされてきた我われ日本人にとっては新鮮でもあります。
さて小学校から被災地に向かった国王陛下ご夫妻を、私は松川浦漁港の被災現場でお迎えしました。相馬市長と紹介していただくと、陛下は手を差し伸べられ、私は市民を代表して訪問の御礼を申し上げながら握手に応じましたが、失礼を畏れずに申し上げれば、陛下は実にさわやかな好青年でした。お妃とは仲の良いご兄妹といった感じでした。
はじめ、松川浦漁港の高台から撮影した震災記録動画をiPADで見ていただきました。組合の市場がコンクリートの柱だけを残して破壊される映像が、いま立っているこの場所で現実に起きたこと、そしてガレキを撤去して一部仮復旧しながらも、獲れる魚に少量ながら放射能が検出されることから、残念ながら漁に出られないこと、あちらで陛下に向かって手を振っている漁師の奥さんたちは、それでも希望を捨てないで仮設住宅で頑張っていることを説明申し上げ、「陛下、畏れ多いお願いですが、彼女らに勇気を与えていただけないでしょうか?」
すると道路の向こうにお進みになり、およそ1メートルの距離まで近づいて陛下がスピーチされました。「私たちは今まで日本から大きな援助と勇気をいただいてきました。この度の震災で被災された皆さんの礼儀正しく統率された姿に感銘し、尊敬の気持ちを持っております。ブータン国と日本は強い友情で結ばれています。私は助け合い励まし合うつもりでここにきました。皆さん希望を持ってください」
1964年に海外青年協力隊としてブータンにわたり、農業の改善に尽くして彼の地に没した西岡京治さんのことをお話になっておられると思いました。Google earth で見るブータンの国土は、山の斜面に幾層にも重なる棚田が美しい。きっと人々の気持ちも美しい国なのでしょう。市民に対して、陛下にこのように言っていただけるご功績を残された西岡先生にも敬意を表したいと思います。
次に尾浜海水浴場の駐車場に移動しました。今ではガレキもすっかり片付いてコンクリートの基礎だけが無機質に続く尾浜地区の被災状況を、A4判のパネル7枚を使って説明させていただきました。印象的だったのはパネルを覗き込むお妃の悲しげな表情です。国王陛下から常に一歩下がって、ともすれば私より後ろに位置取りをされる控えめな方でしたが、あの方は豊かな方だと思います。この平地になっている住居跡には2000人を超える人々が平穏に暮らしていたこと、そのうちこの地で146人が命を失ったこと、相馬市全体で言えば6000人を超す人々が家を流されましたが、9割の方々は避難をして尊い命を失わずに済んだこと、避難誘導に当たった消防団員の勇気によって多くの命が助かったものの、10人の団員が職務に殉じたことをご説明したとき、陛下は大きくため息をつかれました。「ですから我われ相馬市民は、相馬市が続く限り彼らのことを忘れてはならないのです。5月には、私たちが立っているこの場所で、日本国天皇皇后陛下に被災者のための祈りを奉げていただきました。まことに恐縮ですがブータン国両陛下にも黙とうを賜れないでしょうか?」
陛下がお着きになる前に3人の僧侶の方が、すでにお祈りを済ませた小さな祭壇とカーペットが敷いてありましたが、頷いた陛下はカーペットにお進みになり、私に隣に来るように手招きをされました。そうすると私はお二人の間に割って入るようになるので、さすがに遠慮申し上げたいと思いましたが、お妃も当然のように離れて私の場所を空けるので、已む無く私が中央の位置取りになる形での黙とうが始まりました。
僧侶の方がお経を唱えながらの数分間でした。私はいつものように、亡くなった親戚や知人の顔を思い出しながら合掌しましたが、もう一つはお若い国王ご夫妻のこれからの人生に、幸多からんことを祈らずにはいられませんでした。
やがてお別れの時間となったので、私は絶版となった「そうま駒焼」の一対の湯飲みと、相馬市災害対策本部発行の「中間報告書」を記念に差し上げ、「お幸せな人生を」とお二人に申し上げてお送りしました。
私はお二人のひた向きさに、大きな勇気をいただいたような気持ちでした。子どもたちも市民も同じような感慨をもってくれたのではないかと思っています。将来にむけての相馬市の復興は私たちの仕事ですが、ブータン国の今後において、陛下にはどうか勇気をもって立憲君主国家のリーダーとして困難を乗り越えていただきたいと願って已みません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
秘書課 秘書係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2115
- あなたの評価でページをより良くします!
-
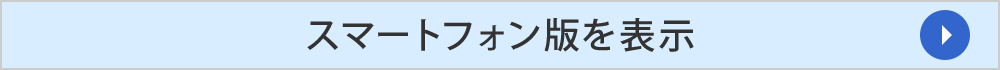


更新日:2019年06月07日