メールマガジンNo.254(2011年6月12日号)相馬市復興計画
6月3日、今後の相馬市の復興の方向性を協議するために「相馬市復興会議」を立ち上げ、議論すべき課題を検討項目として私なりに整理して提示した。ただ現段階で、3年後、5年後の被災地の姿や、被災した方々の望ましい生活像を描き切れるかといえば、かなりの無理がある。国の制度を変えないとどうしても進めない部分もあるし、何より財源の見通しが立たないと夢話に終わってしまうから。
この3カ月、被災による健康や精神へのダメージを最小限に抑え、また原発など二次的な被害から地域を崩壊させないことを最優先に対策本部を運営してきた。次々に発生する難問に、ひとつひとつ丁寧に、迅速に対処するため、市役所はじめ市民が一丸となって頑張ってきた結果、少なくとも対応の遅れで死者を出すことは無かった。特に対策本部員はほとんど休みも取らず、よくやってくれたと思う。
被災して間もないころに政府が立ち上げた復興会議には、当時、正直言って違和感を覚えた。少なくとも震災後一カ月までは目先の直面する課題解決に夢中で、彼らの議論の中身が、我われには遠い国の話のように思えたのである。
今回の震災は規模が異常に大きく、またそれぞれの被災市町村によって状況がすべて異なる。何より、「元に戻せば復興」とはいかないことが大きな特徴であり、それぞれの地域特異性ゆえに復興の定義も多様である。
多かれ少なかれ、何らかの原発被害を受ける本県の各市町村と岩手宮城では、全く違ったプロセスで復興が進むだろう。また本県の中でもそれぞれの市町村によって、被害の実態も、復興に対する考え方もすべて異なる。相馬市のことは相馬市でなければ決して分からないのだから、自分たちで脳みそに汗をかきながら復興計画を練り上げ、育て上げていくべきである。政府の復興会議は被災市町村と緊密に連携しながら、現実を踏まえて復興策を議論すべきだと思う。
大津波による大規模被害の最大の特徴は、復旧が決して復興にならないことだ。相馬市でも被災地にある程度の居住制限をかけたうえで、新たに生活の場と産業を再構築していかなければならないのだが、津波で瓦礫の原となった被災地の将来的な扱いについては、我われだけの知恵と体力だけでは如何ともしがたい。この際、職住分離が基本的政策になるが、被災地を職業領域やソーラーなどの生産基盤にしようにも、公用地として土地利用を進めなければ、いずれ住民の財産権と衝突することになろう。だからといって被災市町村にとって、集団移転促進事業法律(S47)で定める25%にもなる土地買い取り料負担は困難だ。せめて負担を10%以下、できれば5%に抑えられる交付金が必要である。
実現できれば被災者の生活支援にもなる。
住居については高台移転が無論望ましいが、現段階では移転の絵は描けても、その後の人生設計までは企画出来ない。高台に作った災害公営住宅を将来(7.5年後)安価に売却することが出来ないのだ。この点は大震災復興特区で制度の壁を突破できるよう国に要請していきたいと思っている。
もうひとつ重要なことは、復興に至るまでの長い道のりをマネジメントすることである。どんな立派な復興計画をたてても、途中で孤独死や自殺者を出したのでは情けない。だから復興計画には最終の姿に至るまでの管理計画も含まれる。仮設住宅での健康管理、孤独死防止、子どもたちのPTSD対策、瓦礫撤去の際の作業員の健康管理、地域経済活性化、放射能問題対策など予想される多くの課題についての対策も当然復興計画の一部である。これらの問題をのり越えてはじめて復興のステージに立てると考えれば、おのずから中心テーマは被災した市民の生活再建ということになる。多少おおげさかも知れないが、私が考えるに、何をもって「復興」を定義するかと言えば、それぞれの世代で被災者の人生設計が可能になることではないだろうか。
子どもたちの将来のために充分な教育体制を築き、孤児・遺児には生活支援をしながらしっかり育てること。特に単独世帯をはじめとするお年寄りには、安心な生活と医療介護体制を提供すること。
青壮年の世代には産業の復活と雇用の確保。
これらの大きな課題を達成するために、瓦礫を撤去して土地利用を図り、安全で安価な住宅を提供し、また漁港や農地を復旧するのだ。さらに、土地利用の知恵を縛り、住宅取得の無理のない方法を考え、漁業や農業の新しい経営方法や事業形態を生み出し、それぞれの年齢層で将来像が描けるようになるために、ハード事業を細心の注意を払って展開していこうと考えると、復興計画の意味が見えてくるようになる。
また、復興計画は今後発生するであろう新たな問題や、国の対策の規模、範囲、深さ、きめ細かさの如何によっては当然変化と進化をすべきものである。
相馬市はここ数年私のマニフェストを、市が認証を受けているISO9001に基づいて、PDCAサイクルを廻すことによって実現する手法を用いてきた。今回の復興計画も2011バージョン1として作ればよいのだ。来年はPDCAサイクルによりバージョン2として進化させればより実効性のあるものが出来るだろう。過去に認証を受けたISO14001の精神や手法も、環境影響を最小限に抑えるために役に立つに違いない。
ISOを展開するのに必要なことは軸(理念)がしっかりしていることである。復興にあたって軸は、「それぞれの年齢層での人生設計が描けるようにソフト事業を。その為にハード事業を適切に実行」ということになるが、新たな課題の解析と対応とか、達成度のチェックとか、手法の見直しとかを相馬市が慣れ親しんだやり方で自信を持って目的達成に走ればよい。
計画立案にあたり、客観的な評価とさらなる知恵を求める目的で復興顧問会議を置き、各界の有識者に顧問にご就任いただいた。座長には早稲田大学マニフェスト研究所の北川正恭教授、ほか東京農大学長の大澤貫寿氏、元国交省技監で現在国土技術センター理事長の大石久和氏、元国税庁長官で現在日本損保協会副会長の牧野治郎氏、東大医科研の上昌広特任教授、ローソン社長の新浪剛史氏、難民を助ける会理事長で立教大学教授の長有紀枝氏。相馬市においでいただいたことのある方のなかで、私が私淑する7人の有識者にお願いしたところ先生方には快くお引き受けいただいた。我われの立場に立ってご議論いただけるものと期待をしている。
これから各課題の具体策な方法論と、財源根拠の精査に入るが、7月中にはバージョン1-1を、顧問会議のご指導を得て、市民と相馬市の支援者の皆さまに提示したいと考えている。その際ホームページにアップするので、特に今回の震災で相馬に支援においでいただいた方や、遠くから寄附を寄せられて間接的にも今日までの復旧・復興作業に参加された善意の皆さまからも、広くアドバイスをいただければ有り難い。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
秘書課 秘書係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2115
- あなたの評価でページをより良くします!
-
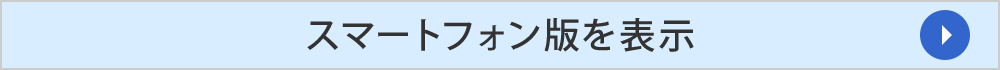


更新日:2019年06月07日