メールマガジンNo.252(2011年5月20日号)新しい村
震災から今日で70日を数える。仮設住宅への移転が順調に進んでいるとはいえ、まだ800人余りの方々が避難所暮らしをしている。全員の方々の仮設住宅への移転が完了する6月中旬まで、対策本部としては毎日の会議を継続中である。健康のため交代で休むよう指示してきたが、気がつけば、私が東京への出張で一回だけ本部会議を欠席した私以外、部長以上の幹部は全員が毎日出てきている。避難所閉鎖をもって、日曜日は本部会議を開かない、公休日にしようと思っているが、あと三週間余りだからこのまま無休で頑張ってもらいたい。
さて、震災直後は合計4400人にも膨らんだ避難所を眺めて、仮設住宅を一日も早く完成させることと、この避難所から一人でも死者を出さないことに闘志を掻き立てた。市内の医療機関の頑張りと、日本医師会、全日本病院協会、東京医大と東京都チームの方々の医療支援活動や、多くの市民、協力団体のボランティア活動により、私の当初の大目標は達成できそうに思える。避難所のうち中村二小の体育館には両陛下にお運びいただいて、一人ひとりお言葉をかけられた。さらに被災した現地でご説明を求められた私は、消防団員たちの犠牲の上に生き延びた人たちの命があるのですと申し上げたところ、小雨の中、傘をお取りになって英霊たちに黙礼を賜った。両陛下のお陰で私もすこしだけ、許してもらえたような気がした。
彼らが残した子どもたちへの、私の気持ちを前回書いた。しかし津波の生存者の今後の生活支援を、しっかり行っていくべきことも彼らの残したメッセージである。いま被災者全員の生活状況をデータベース化しているが、最初にこの災害で単独世帯になった人、つまり家族でたった一人助かった人たちのリストを作って対策を講ずることにした。二次災害として医療の次に留意すべきは、経済自殺と孤独死だからである。調べてみると93歳男性を筆頭に110人の方が単独世帯になっていた。中には、自分だけ助かったことを悔やんでいる人もいるという。
仮設住宅への入居を中期計画の目標にしてきたが、これらの方々の仮設住宅での一人暮らしには、特に長期的な支援を、と思っている。なによりも寂しさ対策と励まし合いが必要だ。一つの方法として複数で住むことを奨めてみたが、全員が独りで住みたいという。ならば集会所で一緒に食事をとりながら、最低でも一日一回のコミュニケーションをとってもらおうと考えて、夕食は配給制にすることにした。よって一年間は仮設住宅入居者全員に夕食を提供するが、独居世帯者には集会所で食べてもらう。また、健康チェックも含めて、顔合わせと会話の機会を積極的に作っていきたい。
独居世帯も含めて、仮設住宅での生活をお互いに支え合いながら過ごしてもらうために、出来るだけ元の地域ごとのコロニーを、集会所ごとに作っていきたいと考えている。およそ80戸でひとつの集会所を囲む形になるが、一棟五世帯ごとに戸長を選び、集会所ごとの戸長会議を組長が束ねる。組長を行政区長が兼務するケースも出てくるが、組長協議会の上に区長会議を位置づけ、行政サービスをこの組織図で行う。したがって住民健康診断をはじめ、支援物資の配給や、外部からの炊き出し部隊のサービスなどは、区長会議と組長協議会で整理する。
相馬市の場合、原発事故のため避難生活を余儀なくされる双葉地方をはじめ、飯舘村や南相馬市の避難民の方々を受け入れることになるが、ふるさと自治体ごとのコロニーを作ることと、行政サービスの葉脈を作ることが、慣れない地域で過ごしてもらうためのポイントである。
相馬市のエリアでは集会所ごとに市の担当者を張りつけるが、他の自治体からのコロニーには役所の職員が一世帯以上住んでもらいたいと考えている。71戸の住民をお預かりすることを決めた飯舘村長とは、村職員居住を申し合わせた。現在、市外から多くの申し込みをいただいているが、以上の理由により最終的には首長さんと調整して入居受け入れを決めさせていただきたい。あとは、他の自治体からの仮設住宅入居者を相馬市民同様、市民全員の力で大切にさせていただくことだ。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
秘書課 秘書係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2115
- あなたの評価でページをより良くします!
-
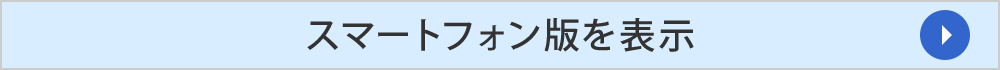


更新日:2019年06月07日