メールマガジンNo.250(2011年4月4日号)消防法被
あの時に、家族を振り切って避難誘導に向かった団員たちのご遺体が、次々と消防法被姿で発見されるなか、長らく行方不明だった稲山分団長が無言の帰還を果たした。とても責任感の強い人だったから、最後まで住民避難に走り回ったのだろう。私に、郷土を想って殉職した怨霊の一分でものり移ってくれと念じ、クローゼットにあった消防法被を着けて執務することにした。
残された家族たちは、しかし、現在7か所に整理された津波被災者の避難所で健気に整然と暮らしている。ブロックごとにリーダーを立て、規律正しく、諍いもなく、笑顔を絶やさずにである。
家族を失い、家を失い、生活手段を失った被災者を支えているのは、地域のコミュニティであり彼らの礼節である。浜で育った私もそうだが、被災地の、自然を畏敬する漁労集落の人々の社会感・人生観は、集団の一員であることを特に大事にする。
外国人が驚嘆する日本人の落ち着きが、もっとも著明に顕れているのは、この相馬の避難所に違いない。
三週目に入った頃に対策本部チームと避難所に一日二回、ラジオ体操を指示した。我われは学童期から団体行動を刷り込まれて育ってきたが、その最たるものが夏休みのラジオ体操だったと思う。外国人から見れば違和感のある光景かも知れないが、非常時に個人主義はなじまない。規律正しい団体行動をラジオ体操が思い出させてくれた。音楽に合わせて全員がそろって手や足を振る姿は逞しくもある。
私をはじめ、被災後の相馬市役所に休日は無く、朝から深夜まで不休の仕事が続くが、疲れとか、ストレスだとか、弱音を吐くものはいない。無くなった方の無念や、被災者の落ち着きと悲しみを想えば、我われはまだ楽だ。しかし、想像もつかないほどの長丁場になることを考慮し、私と副市長、それに部長たち以外は交代で休みを取ることにした。市役所が身体堅固であることも責任の一端だと思うから。
一緒にラジオ体操をしてくれるボランティアの協力があってこそ出来る交代休養だが、兵糧の援助だけでなく、市内外からやってくる優しい気持ちが私や被災者の心を温めてくれる。
災害対策は中期計画に入ってきた。
短期対応は「救命」と「衣食住」だが、中期的な重点課題は「医職住育」。今回の相馬の場合「備える」を加えて「医職住育備」となる。
災害発生から今日まで、救命と捜索、ライフライン、初期医療体制の確保、また原発騒動もあり困難だった食糧・物資獲得や放射能不安対応に専心した。領域が広範にわたる捜索はまだまだ続くが、ここに来て中期的な課題が急務となってきている。
まず、避難所となっている教室を開けて、学校を再開しなければならない。避難所の再編成のためには入所者を減らさなければならないので、賃貸住宅や公営住居へのあっせんと移住をすすめてきた。既存住居への自立支援件数が、学校の教室を確保できる分だけは見込めるようになったので、四月下旬までには再開出来そうだ。したがって中期的な「育」には何とか到達できそうだが、細かい課題は依然として多い。
次の目標は仮設住宅のへの自立だ。仮設住宅は県が建設するとされているが、相馬の場合、市で段取りして一刻も早く作りたい。地域主権論、地方政府論から申し上げれば、直接住民と向き合う基礎自治体に事務能力があれば、任せてもらいたいのだ。阪神大震災の時は神戸市役所に仮設住宅建設の事務委譲がなされたが、今回は県から相馬市への事務委譲を強く求めている。
「医」はライフラインそのものだということも、また総合産業だということも今回わかった。災害医療だけでも膨大な経験をしたが、まだ最終的な医療体制を構築していないので、地域全体の将来設計も含めて今後慎重な議論が必要である。気が遠くなるほど道のりは遠いが、いずれまとめて報告したい。
「職」はもっとも厳しい問題である。これには経済的な危機も含まれる。漁船を漁港もろとも失った漁業者も、田んぼを海水に没した農業者も、生活の手段を失っただけでなく、債務が容赦なく追いかけてくるのだ。この件に関して、我われ市政はあまりにも非力である。国家的な課題として取り組んでもらわないと、災害自殺者が生まれかねない。相馬市では弁護士無料法律相談を県弁護士会に要請したが、被災者の心の拠り所になってくれないだろうか?しかし根本的には、何でもいいから被災者に仕事をしてもらい、収入の道を探ることが一番の解決策である。私が仮設住宅建設を市の事務として、地元工務店に発注したいと切望するひとつの理由である。
重点事項の最後は放射能拡散に対する「備え」である。私は国から避難指示が出ない限り、市民に避難を呼び掛けることはしない。そのことは前回も書いたし、市民も納得していると考えている。しかし万が一、避難指示地域に指定されることがあったら、その時はある程度の時間をかけて、落ち着いて集団避難することを準備しておかなければならないし、市民も頭の隅に置いてもらわなくてはならない。その可能性に対し、気持ちを緩めないためにもリックサックを一家庭にひとつずつ配ることにした。イザという時のセットを入れておいてもらいたい。入院中の患者については、ある広域医療法人に全て受け取ってもらえる了解をいただいているが、取り越し苦労に終わってほしい。老人ホームなどの介護系入所者についてはこれからだが、在宅の災害弱者も改めて調査中である。
今や物流はほぼ回復したが、基本的な食糧の備蓄は進めている。現在米は市民一人あたり4キロ、水は4リットルを備蓄した。味噌と梅干しも相当量集まったが、現在も貯蓄中である。
前回のメルマガで、「米と梅干しと味噌さえあればろう城できる」と書いたが、十日たった今は多くの店がオープンした。呼び水になったのはローソン。新浪社長とはこの件ではじめて知り合ったが、お互い意気投合して相馬店の再開方法を何度も話し合った。積極的で企画力にあふれる彼が、ついに相馬店をオープンさせてくれた時は暗闇に明かりが灯る思いだった。その他、東京医大臼井学長、東大の上教授、中村教授、女子医大田上教授、徳州会徳田理事長にも温かいサポートをいただいている。この稿を借りて深謝したい。
相馬市では現在まで378体のご遺体を収容したが、未だ200人余りの捜索対象者がおいでになる。今後も懸命の作業を続けなければならないが、一方、中期的な課題解決は、同時に相馬市の将来像や相馬地方全体の復興ビジョンを視野に入れた長期計画の始まりでもある。この戦いがいつまで続くか計り知れないが、まだ始まったばかりであることは間違いない。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
秘書課 秘書係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2115
- あなたの評価でページをより良くします!
-
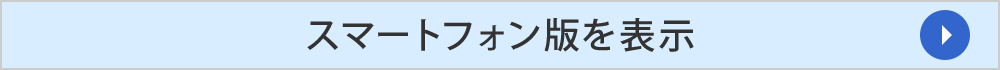


更新日:2019年06月07日