地域計画(旧 人・農地プラン)
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
国は、「人・農地プラン」を法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化などを進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正法を令和4年5月に成立させました。
市は、これまで地域での話し合いにより、「人・農地プラン」を策定・実行してきました。しかしながら、今後、高齢化や人口減少の本格化により、農業者の減少や遊休農地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなってきていることから、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化などに向けた取り組みを加速化することが必要です。
これまで地域の皆さんが守ってきた農地を、次の世代に着実に引き継いでいくため、農作業がしやすく、手間や時間、生産コストを減らすことが期待できる農地の集約化などの実現に向け、幅広い意見を取り入れながら、地域の関係者が一体となって話し合い、将来の農地利用に関する「地域計画」を作成します。
地域計画とは
地域農業の将来を話し合いにより、策定しました「人・農地プラン」に、10年後の耕作者をあらかじめ決めておき、地域農業の状況などを見える化した目標地図を加えたものが「地域計画」です。
各地区で座談会を開催し、地域の関係者との話し合いを通して作成します。
作成期間
4月1日~令和7年3月31日
対象地域
市街化区域などを除いた市内全ての区域(全35地区)
(補足)原則大字単位とし、一部集落単位で作成
関係機関
市農林水産課、市農業委員会、県相双農林事務所、県農業振興公社(農地バンク)、ふくしま未来農業協同組合(JA)、そうま土地改良区 など
協議の場の結果公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、市内各地区で実施した協議の場の結果を公表します。
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告します。
地域計画の主な関連施策(農林水産省ホームページより)
地域計画と連動する補助事業一覧 (PDFファイル: 88.8KB)
農業経営基盤強化準備金制度 (PDFファイル: 431.7KB)
人・農地プランとは
農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などの理由で、5年後~10年後の農業の展望が描けない集落や地域が増えている中、集落や地域での徹底した話し合いにより、地域の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)や農地の確保、経営体への農地集積の方針を定め、今後の地域農業のあり方や、基本となる人と農地の問題を一体的に解決し、農業の競争力や体質の強化を図り、持続可能な農業を実現することを目的とした地域農業のマスタープランです。
人・農地プランの実質化
市は、令和元年度から国の方針により人・農地プランの見直しおよび実質化に向けた取り組みを開始。
実質化とは、下記の手順を行うことにより、現在の人・農地プランを真に地域の話し合いに基づくものにすることであり、実質化を行うことが今後の担い手育成や農地集積に係る交付金・補助金の要件になります。
1 アンケートの実施
対象地区において、おおむね5年から10年後の農地利用に関するアンケート調査を実施。
2 現況把握
対象地区で行ったアンケート調査や話し合いを通じて、農業者の年齢階層別の就農や後継者の確保の状況を地図により把握。
3 今後地域の中心となる経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成
対象地区を原則として集落ごとに細分化し、5年から10年後に農用地利用を担う中心経営体に関する方針を作成。
実質化した人・農地プラン
市は、これまでの取り組みによって現在の人・農地プランがすでに実質化しているかの検証を行いました。その中で「実質化していない」と判断した区域に関し、実質化の手続きを行いました。実質化した人・農地プランは以下の通りです。
実質化された人・農地プラン(中野・西山地区) (PDFファイル: 484.4KB)
実質化された人・農地プラン(和田・本笑・北飯渕地区) (PDFファイル: 486.2KB)
実質化された人・農地プラン(塚部・長老内地区) (PDFファイル: 499.8KB)
実質化された人・農地プラン(椎木地区) (PDFファイル: 479.4KB)
実質化された人・農地プラン(初野地区) (PDFファイル: 479.6KB)
実質化された人・農地プラン(黒木地区) (PDFファイル: 504.9KB)
実質化された人・農地プラン(粟津地区) (PDFファイル: 484.7KB)
実質化された人・農地プラン(山岸・須萱地区) (PDFファイル: 551.3KB)
実質化された人・農地プラン(金谷原・物倉地区) (PDFファイル: 522.8KB)
実質化された人・農地プラン(今田地区) (PDFファイル: 502.1KB)
実質化された人・農地プラン(富沢地区) (PDFファイル: 505.5KB)
実質化された人・農地プラン(馬場野地区) (PDFファイル: 477.9KB)
実質化された人・農地プラン(赤木地区) (PDFファイル: 469.0KB)
実質化された人・農地プラン(古磯部・金草地区) (PDFファイル: 508.7KB)
実質化された人・農地プラン(西玉野地区) (PDFファイル: 524.6KB)
実質化された人・農地プラン(東玉野地区) (PDFファイル: 503.7KB)
既存プランの実質化検証基準
人・農地プランの区域の全部または一部のうち、対象地区内の過半数を超える農地が、近い将来に農地の出し手と受け手が特定されている区域であることが、既存の人・農地プランの実質化検証基準になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農林水産課 農業振興係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2147
- あなたの評価でページをより良くします!
-
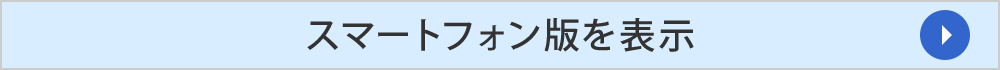


更新日:2025年02月04日