縄文から平安時代
縄文から平安時代にかけての相馬のできごとは下表のとおりです。
| 時代 | 日本のできごと | 相馬のできごと |
|---|---|---|
| 縄文 | かりや漁のくらし(約1万年の間続く) | ― |
| 弥生 | たて穴式の住居、石器や土器 | 地ノ内遺跡 |
| 弥生 | 米作りが今から2300年ほど前大陸から伝わる 小さな国があちらこちらにできる |
― |
| 古墳 | 古墳が各地につくられる | 丸塚古墳よりはにわ(人物・馬など)出土 |
| 古墳 | 大和朝廷の国土統一が進む 仏教が大陸から伝わる 聖徳太子が十七条の憲法を定める(604) 中国(隋、唐)に使いを送るようになる |
― |
| 飛鳥 | 大化の改新(645) | ― |
| 奈良 | 奈良に都を移す(710) | ― |
| 平安 | 東大寺の大仏ができる(794) | 黒木田遺跡(寺院または官が跡)より古瓦出土 |
| 平安 | 京都に都をうつす(794) 藤原氏がはじめて摂政になる(866) |
― |
| 平安 | ― | 相馬氏の祖と伝えられる平将門が下総国小金が原で野馬を敵に見立てて戦いの演習を行ったと伝えられる |
| 平安 | 藤原道長が摂政になる(1016) 鳳凰堂ができる(1053) 武士の力が強くなる 平氏が栄える |
― |
| 平安 | 源氏が平氏を滅ぼす(1185) | 宇多郡(現相馬市)を平泉藤原氏が支配と推定 |
| 平安 | 源頼朝が平泉の藤原氏を滅ぼす(1189) | 相馬師常が奥州行方郡(現南相馬市)の支配を認められた(1189) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生涯学習課 文化係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2100
- あなたの評価でページをより良くします!
-
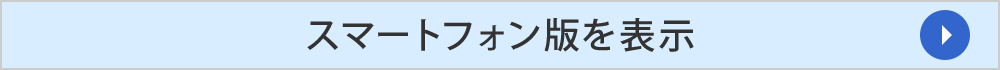


更新日:2022年12月09日