八幡神社本殿・幣殿・拝殿
はちまんじんじゃ ほんでん・へいでん・はいでん

神社由緒に、建武年間(1334〜1338)、宇多庄の守護白川道忠(結城宗広)によって建立されたとあります。
現在の建物は、1695年(元禄8)、藩主相馬昌胤によって再興・造営されたものといわれています。
建物全体は、流造風の本殿と入母屋造の拝殿とを、拭板敷(ぬぐいいたじき)の幣殿でつなぐ、いわゆる権現造りの形態をもつ社殿となっています。また、全般に入念な手法が施され、板壁外面や脇障子などの文様彫刻、内・外陣の板壁内側や天井には鮮やかな絵が描かれており、元禄時代を彷彿とさせる建造物です。
昔は、祭礼に流鏑馬が行われていたともいわれています。
本殿内陣に安置されている「宮殿(くうでん)三基」、拝殿に掲げられている沙門慈胤書の八正宮の「扁額一面」も、国重要文化財に指定されています。
指定の区別
国 重要文化財(建造物)
所有者/管理者
八幡神社
所在地
相馬市坪田字涼ケ岡51
指定年月日
平成24年7月9日
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生涯学習課 文化係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2100
- あなたの評価でページをより良くします!
-
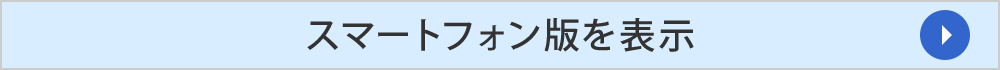


更新日:2019年12月23日